タイトル通り。覚え書き。散漫的に書いていきます。
全般的な話
参考書ルートの参考書多すぎ問題
指導する上で、どういった参考書がいいのかを知るべく、ネットで調べたり本屋に長居して参考書を比較検討してみたりしています。
特に、受験界隈では”参考書ルート”という概念があります。
要はこれは、ある参考書をやったあとに次にどの参考書をやれば〇〇大学合格レベルまで行く、といったような参考書をやる順番をルートとしてまとめてくれているものです。
受験生は、膨大な数ある参考書の中から、自分ひとりで色々試して現在の自分に最適な参考書を選ぶほどの時間的余裕はないので、そういった参考書ルートに頼るわけです。
さて、この参考書ルートについてですが、「巷であふれる参考書ルート、使う参考書多すぎないか?」と最近思ってしまっています。
そりゃ東大とか目指すなら話は別でしょうが、最難関を目指す人など割合で言えば極々一部。
それ以外の多くの人にとっては、巷で見る参考書ルートの参考書は数が多いと思います。
例えば数学は網羅系、例えば有名どころでいうと『1対1対応の演習』を完璧にした場合(※例題だけでなく演習題も含む)、それプラス過去問で対応できない大学は全国に20校も無いのではないのではないでしょうか。
参考書のつまみ食い有効説
参考書をたくさん比較してみて思ったのですが、良い/悪いと言われている参考書であっても、ある単元は悪い/良いということが普通にあります。
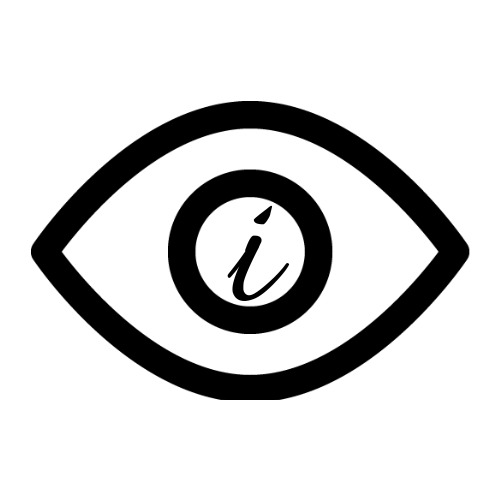
数学が特に顕著な気がします。
最高効率を求めるなら、単元Aはこの問題集、単元Bはこの問題集といったように単元別で問題集を集めるのがいいと思いました。
ただ勿論、受験生でそのような比較検討ができるほど余裕のある人は少ないでしょう(費用もかさむし…)。
適切な指導者が問題を選んであげる必要があります。
「1冊を完璧に」というのがもう受験常識のようになっていますが、それは果たして本当なのかと思いました。
予備校講師の神格化に注意
当たり前の話ですが、予備校講師は職業です。
つまりお客さん(生徒)がいないと困ります。
競争率の激しい中、予備校講師として生き延びるためには生徒からの人気を集める必要があるわけです。
そのために生徒をアッと驚かせたり、授業内容についての納得感を与えたりする必要があるわけですが、その手法が極端な方もいらっしゃいます。
派手な言葉遣いや大きな声など、授業以外の面で生徒を引きこむのもその一例。
他には、大学レベルの難しい内容ばかりを披露したりして、生徒に「この先生すごい!」と思わせる人など。
高校生相手に大学の内容まで踏み込んで話していれば、そりゃ当然生徒は毎回何かしらの新しい知見を得ることができます。
ただ、一部の大学を除けば、大学入試のほとんどの問題は基本的な問題で構成されます。
つまり、当たり前のことを当たり前にできるようにするのが先決です。
しかし、それを授業で淡々とやってしまうと生徒は退屈ですし、少なくとも「この先生すごい!」とはなりづらいわけです。
そういうわけで、”派手なこと”をやって人気を獲得する講師も現れるわけです。
影響を受けやすい中高生が、講師の人格やバックグラウンドに惹かれたりしてしまうのも分かるのですが、授業の内容自体が入試に役立つことをやっているのかどうかは、きちんと疑いつつ受講してほしいなと思います。
いくつかの科目について
いくつかの科目について気になったこと。
英語
英作文(日英翻訳)の問題集をみてると、明らかに全く訳していない部分があったり、どう考えても意味が変わっている部分などが散見されます。
というのも、大学受験の英作文は、日本語で書かれた文章を簡単な日本語で置き換えて、そこから英語にするというのが王道指導法の1つになっているのです。
大学入試の採点基準は、大学の先生以外は誰も分からないことなので、そのある意味”逃げ”の戦法がどれほど通用するのかは皆わからないはずです。
そういった点を踏まえて問題集を見たうえで少し不親切だなと思う点が、参考書に載っている英作文の解答が、減点覚悟の”逃げ”なのか、満点解答なのかがわからないということです。
参考書を書いている先生的には「高校生にこんなん書けないからこれで書いとけ」ってことなんでしょうけど、それについての説明を付記してほしいなと思います。
例えば「これは満点解答を書くのは無理なのでこれで誤魔化して7割を狙いましょう」といった文言とともに解答を載せてほしいです。
実際「なぜこの解答でいいのか?(≒これは満点解答なのか?)」といった質問はよく受けます。
物理
物理という科目は、できる人とできない人ではっきり二分されるようです。
私は、「独学で最も早く合格点を取れる科目はなにか」と聞かれたら間違いなく物理と答えるのですが、どうやら「物理は独学では厳しい」という声は大きいようです。
別に私も物理のプロではありませんが、教科書レベルから分からないというのは、言葉を選ばず言えば、気持ちが全く理解できません。
私自身、物理は独学で進めましたが、高校の科目の中では抜きん出てシンプルに思えました。
覚えることも少なく、また数学に比べれば問題のパターンはかなり少ないので、基本事項を押さえて問題演習すれば一瞬で成績が上がります。
……と、こういった自分の成功体験で科目を語るのは、指導する立場としては非常に良くないわけです。
物理を諦めた人というのは、そのほとんどが物理基礎で諦めた人だと思いますが、物理基礎のどこでどのように詰まってしまう人が多いのかについて、勉強をしなければならないと感じました。
数学
ほとんどの大学は網羅系を完璧にすれば十分ではないかという旨を先述しました。
一方、最難関大学の数学は、典型問題をマスターしたからといってスパスパ解けるものではありません。
まず、網羅系にあるような典型問題の次に、”難関大レベルの典型問題”というのがあります。
これは大体、一昔前には難問だったのですが、いろんな大学で出されるうちに典型問題となったものです。
典型問題といっても別に簡単なわけではないという、勉強のしづらさがあります。
また、解法選択の難しい問題というのもあります。
例えば図形なら、ベクトルで攻めるのか三角関数で攻めるのか、はたまた座標で攻めるのかなど。
こういったものを解法ベースで体系立ててまとめてくれている参考書があったら良いな、と思います。
そういったものは無くはないものの、かなり少数です。
『入試数学の掌握』シリーズなどはそれですが、あまりにもハイレベルすぎます。
自分が思いつくものだと、『世界一わかりやすい京大の理系数学』がそれに近いです。
が、タイトル通り問題はすべて京大の過去問ですし、どうしても問題のタイプに偏りが生じてしまいます。
良さげな参考書があったら教えていただきたいです。
情報がたくさんある苦しさ
色々調べてて最も強く感じたことが、受験生からしたら選択肢が多いって大変だろうなということですね。
参考書ルートも参考書レビューも腐る程でてきます。
結局、今自分が何をしなければならないのかを判断するのは至難でしょう。
昔は、「とりあえず目の前にあるものをひたすらやる!」で良かったのでしょうが、今は違います。
たとえ自分が「これだ!」と決心してやり始めた参考書であっても、「その参考書使ってるやつは落ちる」みたいなレビューは探せばいくらでもでてきてしまいます。
高純度の自己分析をし、その上で現状の自分の勉強に多大な自信を持っているという人でない限り、そういったレビューにすぐに影響を受けてしまいます。
受験は情報戦というのは勿論そうなのですが、それと同等以上に自己分析力が大事なのだなと思います。
独学の限界→授業の復活?
ここ十年くらいで(?)、独学というのが1つのトレンドワードになっていると感じます。
大学受験に関しても、そのトレンドはあります。
「授業は非効率で、参考書で勉強したほうが早い」と。
この考えを持っていた人は昔からいたでしょうが、少なくともこの考えの普及に大きな影響を与えたのは、武田塾さんだと思います。
この考え自体は、私も部分的に賛同派ではあります。
皆、得意不得意や進度も違うのに一斉に同じ授業を受けるというのは非効率です。
実際、参考書でやったほうが早い場合が多いだろうとも思います。
ただ、当たり前の話ですが、みんながみんな独学が得意なわけではありません。
今は、独学で大学受験を突破するという概念自体は、全く珍しいものではなくなりました。
その概念がここまで浸透した結果「私も独学でやってみよう」という人は、”大学受験対策は授業前提”の時代に比べて明らかに増えているはずです。
それは素晴らしい事だとは思うのですが、その反面、独学の限界に気づいていく人もこれからどんどん増えてくると思います。
私は独学が好きですが、楽だとは思いません。
多くの場合、授業を聞くよりは進度は早いとは思いますが、当然頭はかなり使います。
理解にずっと苦しんでいるくらいなら、時間がかかってもいいから授業を聞いて理解したほうがいいというのは当然のお話。
脳の使役に耐えられない人の声が積み重なり、「なんだかんだ授業聞いたほうがいいよね!」といった風潮がこれから来るのではないかと思っています。
私も、全くもって授業全否定派ではなく、基本は独学ベースで、部分的に授業を活用するというのがいいのかなと思っている派です。
とりあえず、今回はここまで。
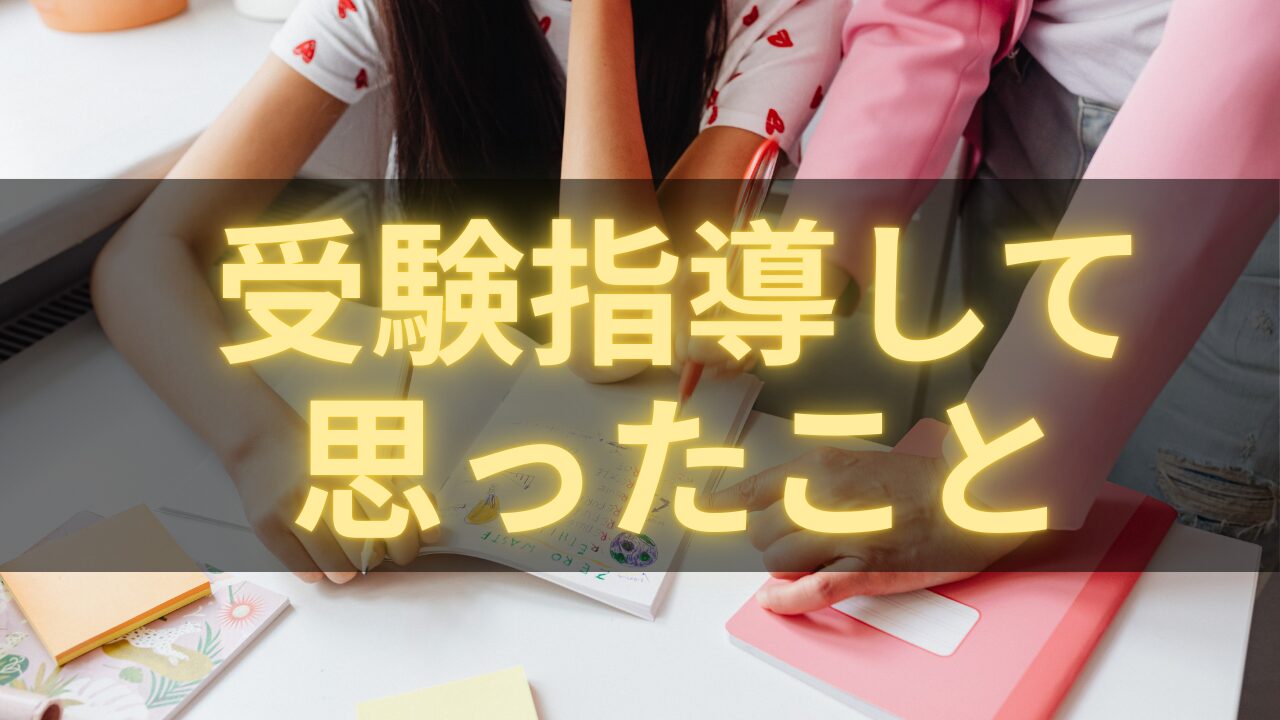
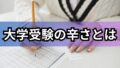

コメント