私は早稲田大学には理系と文系の両方で合格しています。
どちらの受験でも数学を使いましたが、今回は文系学部の一般選抜入試における数学受験ということに特化して話していきたいと思います。
私は早稲田大学の社会科学部に数学受験で合格しました。
当時の倍率は10倍を超えていて競争の激しい戦いとなりましたが、それでも私は受験が終わった瞬間に合格を確信していました。
その理由の8割くらいは私が数学受験だったためです。
早稲田大学の入試の仕組みを見ると、「文系だから」「数学が苦手だから」という理由で大して大して調べもせずに早々と数学受験を諦めるのは勿体無いことが分かります。
数学が苦手な人であっても余程の直前期でない限り、数学受験で間に合わせる努力をしたほうが良いというのが持論です。是非最後までお付き合いください。
早稲田文系で数学受験できる学部は?

※入試方式は毎年変わる可能性がありますので必ず自分で調べてください
具体的に、文系の一般選抜で数学を利用できる学部をあげると
政治経済学部・商学部・社会科学部・人間科学部です。
※法学部も一応数学を使えますが共テ利用ですので今回は省きました。
第一志望なら勿論、滑り止めであってもできるだけ楽に受験を突破したいもの。
滑り止めの場合、合否は精神衛生上の観点から本命にも影響がでます。
さて、この時に選択を迫られるのが選択科目です。
予備校の私立文系クラスにいたりすると周りの殆どが社会選択で、「周りはみんな社会を選んでるから私も社会にしよう…」と思考停止に陥ってしまうかもしれません。
果たして、みんなが社会選択にしているからそれが最善であると言えるのでしょうか?
“標準化による得点調整”というシステムを知ろう

私は社会科学部を受験するにあたって、数学選択と社会選択のどちらが有利なのかをまず自分で調べました。
そして標準化による得点調整というシステムを知りました。
このシステムはどういうものなのか簡単に言うと、ある科目の選択によって有利になったり不利になったりするのを防ぐシステムです。
具体例をあげます。
入試の選択科目でAとBのどちらか一つを選べるとします。
試験の結果、科目Aの平均点が20点で科目Bの平均点が60点だったとします。
佐藤さんは科目Aを受けて60点を獲得、鈴木さんは科目Bを受けて60点獲得したとしましょう。
さて、これで何の措置もない場合、佐藤さんも鈴木さんも同じ60点が入試の点数として使われます。
これは流石に不公平ですよね?佐藤さんは難しい内容の科目で60点も獲得しましたが、鈴木さんはぴったり平均点。
これを公平にしようというのが標準化なのです。
さて早稲田大学の選択科目の場合はどうなっているでしょう。
実際に標準化の計算をしてみよう

入試データを見てみると、数学受験可の全ての学部で数学の平均点は他の選択科目よりも低いです。
少なくともここから分かるのは、社会科目を選択した人と同じ点数を数学でとったらその時点で数学受験者の方が点数が高くなるということです。
「平均点が低いのは難しいからでしょう…?」と思われるかも知れません。
それはごもっともな疑問です。
例えば、数学が難しいと言われる商学部の選択科目別平均点(2019)を見てみますと以下のようになっています。
日本史 38.029
世界史 40.008
政治経済 22.604
数学 16.226
(各60点満点)
数学の平均点が3割未満というのはすごいですね。
ところが実際に問題を見ていただくと意外にも、超高難易度ではないというのが分かります。
もしかしたら高校数学をあまり勉強したことのない方の中には絶対解けない!って思った人もいるかもしれません。
でも安心してください。
数学は間違いなく才能が関係する科目ではありますが、その一方で”数学”ができなくても数学の解法の”暗記”で解けてしまう問題というのは入試問題では山程あります。
それらはもはや数学という高尚なものではありません。
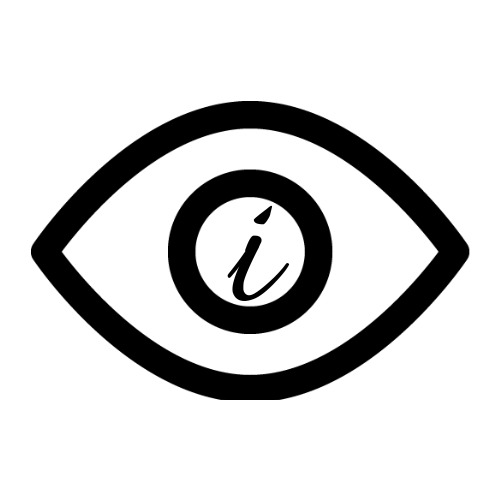
数学を理解することと数学をツールとして使うことは全くの別物なのです。
何より、素点が低かったとしても成績標準化によって点数が大きく伸びえます。
そのことを示すために、成績標準化を実際の入試結果に適用してみましょう。
成績標準化の式は早稲田大学は公表しておらず、いくつかの説がありますがどれを用いても大きく外れることはないと思われます。
今回はこの式を用います。
(素点-平均点)×1.25+満点の半分の点数 = 標準化後の点数
さて、数学が苦手で数学で5割しか取れなかったとしましょう。
すると標準化後の点数は47.2175点となります。
一方、多くの文系勢が履修するであろう世界史で見事8割を取ったとします。
すると標準化後の点数は39.996点となります。
これ見てどう思いますか??
早稲田の世界史で8割とってもこれですよ。
対して数学は5割です!半分です!これで世界史8割の得点者に7点差以上も点差をつけられます。
多少数学が苦手な人でも、数学受験の方が高い点数になる可能性が十分にありえることが分かっていただけましたでしょうか。
「数学が歴史科目より大変」は本当か?
私は元々理系で、世界史Bは完全な独学でした。
それで感じたのは、世界史は思ったよりも”重い”科目だったということ。
私はただ暗記すればいいんじゃないの?と思っていましたが、そんな生易しいものではありませんでした。
そもそも暗記する量が膨大ですし用語を暗記したところで、それらを自分なりに体系的に把握しないと何をやっているのかも分からないし得点にもならない。
上の記事でも書いていますが、最初は本当に試行錯誤でしたね。
対して数学の解法暗記は違います。公式・解法というツールを振り回してパズルゲームをしていくだけ。
勿論これだけでは思考力は鍛えられませんし、解法暗記が終わったらじっくり思考する訓練が必要でしょう。
しかし、良いことなのか悪いことなのか(個人的にはあまり良くない)早稲田大学に限って言えば、数学の得点率が低くても社会選択に勝ててしまうのです。
そうなると話は変わってきます。
数学の理解を投げてツールを振り回す練習をし、大学受験合格を優先するのは受験生としては当然の流れとなってしまうでしょう。
数学の二次関数さえ分からない、かつ歴史は胸を張って大得意と言えるという人ならいざ知らず、迷っている方にはそこまで数学は大変ではない(上述の意味で)ということを知ってほしいです。
自分の頭で考えて自分で決めよう
ここまで数学受験の有利である理由を述べてきました。
私も数学受験を決断するにあたって、不安が全く無かったと言えば嘘になります。
成績標準化を知り、3年分ほど過去問を解いて全てほとんど満点でしたがそれでも不安は拭えませんでした。
なぜみんな数学で受けないのか、自分が何か間違っているのか、見落としがあるのか…色々考えてしまいました。
ネットを見ると、数学受験は賭けという情報もでてきたりしてより不安を煽られます。
しかしそこで情報に踊らされるのはダメなんですね。自分で考えて決めないと。
無論それはこの記事にも当てはまります。私はこの記事で
・数学の得点率は低くても問題ない
・素点でとれなくても実際数学で社会選択に勝てる
・社会と数学の重みについて
などの話に触れ、数学受験が有利であることをどうやったら分かって貰えるかを懸命に考えて書きました。
しかしこの記事を読んで、素直に書いてあることを全て受け入れる姿勢は危険と言えば危険です。
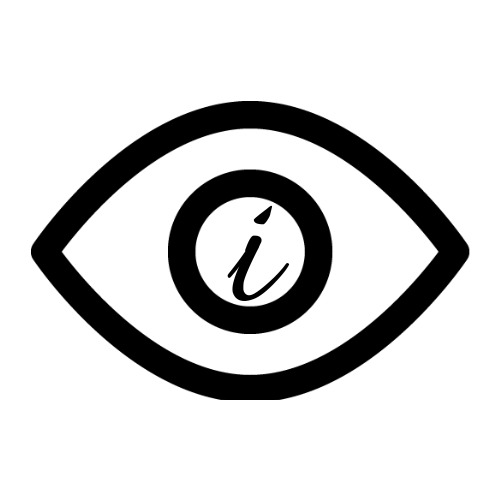
勿論私としては受け入れてもらうのが目標なんですが…(複雑な気持ち)
情報を集めて最後に決めるのはあなたです。是非考えてみてください。
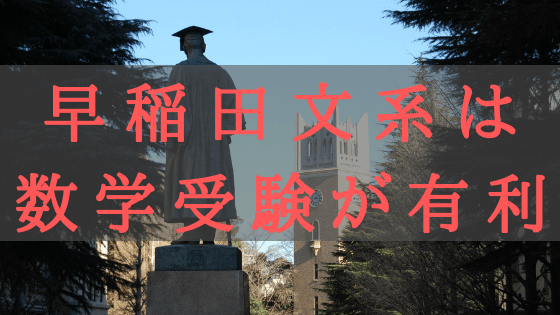

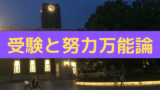


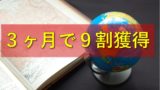


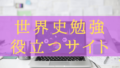
コメント
同じ考えの人がいた